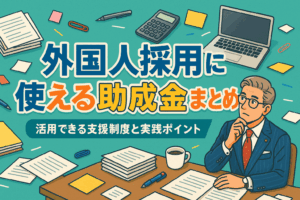【2025年最新版】ホテル業界の外国人採用動向と成功ポイント

新型コロナの水際対策が終了して観光需要が急回復する一方で、ホテル業界では深刻な人手不足が続いています。
日本人従業員だけではサービス提供が追いつかず、外国人スタッフの採用に注目が集まっていますtravelvision.jp。
そこで、ホテル業界の人材不足の現状と背景、外国人採用の動向と課題、
そして具体的な成功事例や外国人スタッフ活用のポイントを総合的に分析します。
人事担当者・経営層が直面する人手不足・定着率・採用失敗リスクといった課題を洗い出し、その解決策を章立てで示します。
目次
ホテル業界の人手不足と外国人採用ニーズの将来動向
深刻な人材不足の現状
宿泊業界ではコロナ前から慢性的な人手不足が続き、コロナ禍で一時的に緩和したものの2023年には従業員不足率が業種別トップの75.6%に達しましたtravelvision.jp。
つまり約4社中3社が「正社員が足りない」と感じている状態です。
2025年1月時点でも5割超の企業が人手不足を実感しておりtdb.co.jp、深刻さが続いています。
「従業員不足」は旅館・ホテル市場における最大の経営リスクとなっており、人手不足への対応が今後の業績を左右すると指摘されていますtdb.co.jp。
直近数年の推移
2022年頃からインバウンド(訪日客)の急増にホテル需要が押し上げられる一方、
人員確保が追いつかない状況が顕在化しましたtdb.co.jp。
帝国データバンクの調査によれば、2024年時点でも正社員の約71%・非正規の約61%が不足と報告され、
他業界と比べても圧倒的に高い割合ですglobal-saponet.mgl.mynavi.jp。
業種平均の求人倍率1.38倍に対し、宿泊業では6.15倍という極端な売り手市場で(後述)、特に「飲食物給仕」(レストランサービススタッフ)の求人倍率は7倍超と突出していますglobal-saponet.mgl.mynavi.jp。
厚労省「職業安定業務統計」にみる職種別の有効求人倍率(宿泊業の主要職種)global-saponet.mgl.mynavi.jp。全職業平均が1.38倍であるのに対し、旅館・ホテルのサービス職(飲食物給仕係など)は6倍以上と極端な人手不足状態にある。
今後数年の見通し
インバウンド好調により宿泊需要は拡大基調が続く見込みで、
国内ホテル市場規模は2024年度に5.5兆円と過去最高を更新する予測ですtdb.co.jp。
一方で労働力不足は2025年度にさらに表面化する可能性が指摘されていますtdb.co.jp。
人材難の長期化に備え、多くのホテルが省人化(チェックイン機の導入等)や外国人材の登用を加速させていますtdb.co.jp。
少子高齢化による国内労働力人口の減少が宿泊業の人手不足の根底にあります。
ホテル業界では他産業に比べ給与水準が低く休日も少ないため若者の確保が難しく、
結果として人材不足が慢性化していますglobal-saponet.mgl.mynavi.jpglobal-saponet.mgl.mynavi.jp。
今後は国内人材に頼るだけでなく、海外人材の活用や業務効率化による生産性向上が不可欠といえますhotelbank.jp。
政府も観光立国に向け「2025年までに訪日観光客6000万人」目標を掲げており、それに伴いホテルのサービス人員確保が重要課題となっていますhotelbank.jp。
以上より、今後数年~長期にわたり宿泊業の人手不足は続く見通しであり、構造的課題への対応が急務と言えます。
ホテル業界における外国人スタッフの現状と活用状況
ホテル業における外国人労働者の現状
人手不足を補う切り札として、近年ホテル業界では外国人採用が急速に拡大しています。
宿泊業での外国人求人は前年比6倍以上に増加したとの報告もありtravelvision.jp、
各社が海外人材の確保に本腰を入れ始めました。
もっとも現在のところ、宿泊業に従事する外国人労働者数は約3.3万人(外国人労働者全体のわずか1.6%)にとどまっておりhotelbank.jphotelbank.jp、製造業など他分野と比べれば受け入れは十分とは言えません。
それでも外国人材なしでは回らない職場も増えているのが実情で、フロントや客室清掃、
レストランサービスなど様々な現場で外国人スタッフが重要な戦力となりつつあります。
職種別の活用状況
外国人スタッフが多く活躍する職種としては、まずフロント(受付)が挙げられます。
英語や中国語など多言語対応が求められるフロント業務では、語学力と異文化理解に優れる外国人材が強みを発揮していますhotelbank.jp。
実際、海外からの宿泊客対応を強化するために外国語堪能な外国人スタッフを意欲的に配置するホテルも増えていますmlit.go.jp。
次にレストランサービス(飲食物給仕)分野でも外国人の比率が高まっています。
宿泊業の中でも食事処のスタッフ不足が特に深刻(有効求人倍率7.16倍)であることからglobal-saponet.mgl.mynavi.jp、
留学生アルバイトや技能実習生など多くの外国人が配膳・ホール業務を担っています。
また、客室清掃・ハウスキーピング業務でも実は外国人が多数活躍しています。
清掃業務は言語ハードルが比較的低いため、技能実習の対象職種ではないものの、
別業種の技能実習生や資格外活動(留学生アルバイト)として現場を支えている例が多く見られます。
その他、調理スタッフについてもホテルによっては海外の料理人を招聘したり、
和食の技能実習で外国人見習いシェフを受け入れたりするケースがあります。
総じて、語学力を活かすフロント/接客系から体力勝負の裏方業務まで、
ホテルのほぼ全職種で外国人材の役割が広がっています。
国籍別の傾向
ホテルで働く外国人の出身国も多様化しています。
外国人労働者全体で見るとベトナム(約25%)が最多で、中国(19%)、フィリピン(11%)が続き、
この3か国で全体の過半数を占めますhotelbank.jp。
宿泊業に限っても東南アジア出身者が多く、技能実習や特定技能でベトナム・中国・ミャンマー・インドネシアなどの若者が来日するケースが目立ちます。
一方で、高度人材枠(技術・人文知識・国際業務ビザ)では台湾や韓国出身の人材がホテルフロントなどに増加していますtravelvision.jp。
マイナビグローバルによれば、現在同社が宿泊業向けに紹介する外国人は台湾・韓国からの人材が中心とのことですtravelvision.jp。
これらの国の人材は日本語能力が比較的高く、日本文化への適応も早いため即戦力として重宝されています。
また南アジア系ではネパールやバングラデシュの留学生アルバイトが飲食・清掃などで活躍したり、
中南米の日系人(ブラジル・ペルーなど)がスタッフとして定着しているケースもあります。
つまり、ホテル業界の外国人材はアジア圏を中心に世界中から集まっており、各国の強み(語学、ホスピタリティ精神など)を活かして配置されているのが特徴です。
地域別(都市部 vs 地方)の採用動向
都市圏の大型ホテルと地方の旅館・リゾートでは、外国人採用の状況に違いがあります。
まず東京都や大阪府など大都市圏では、そもそも在留外国人数が多いため求人募集への応募も得やすい傾向です。
実際、外国人労働者数を都道府県別に見ると東京が約45万人と突出しており、
次いで愛知・大阪が多くなっていますrc.persol-group.co.jp。
東京では宿泊業・飲食サービス業に従事する外国人労働者数も他地域に比べ多いことが確認されていますrc.persol-group.co.jp。
一方、地方部(郊外・田舎)の宿泊施設では「応募者そのものがいない」という深刻な状況がみられます。
若年層の人口流出でただでさえ人材難の地方旅館では、
日本人だけでなく日本にいる海外人材ですら集まらないため
海外在住の人材を直接呼び寄せて採用する動きが広がっていますtravelvision.jp。
例えば北海道や沖縄のリゾートホテルでは、国内在住の外国人応募が乏しいため、
現地エージェントを通じて海外から人材を招くケースが増えていますtravelvision.jp。
この傾向は地方の宿泊施設ほど顕著で、特に山間部・離島などでは
外国人を含め人材確保のために海外リクルーティングに踏み切る事業者もあります。
総じて、都心部ではより優秀な外国人が働き、地方部では外国人採用が必要不可欠だが人材確保策に工夫が求められる状況と言えます。
日本人スタッフの採用動向と若年・高齢層の傾向
若年層の志向と課題
ホテル業界は一見「若者に人気の職種」と思われがちですが、
実際には若手の定着率が低いことが大きな課題です。
新卒でホテル業に就職する人も一定数いますが、3年以内離職率が非常に高い(3割前後)と推定されていますmot-net.com。
宿泊業界全体の年間離職率は14.2%と他業種より高くmot-net.commot-net.com、特に20代の早期離職が目立ちます。
その原因として、労働環境の厳しさが指摘されています。
長時間勤務や夜勤、土日休みが取りづらいシフトなどが若年層に敬遠され、
「プライベートの時間が確保しづらい」「将来のキャリアが見えない」等の理由で転職してしまうケースが多いのです。
また、近年の若者は事務系・管理系・ITなどのデスクワークを志向する傾向もあり、
アナログで拘束時間の長い職場と映るホテル業は就職先として敬遠されがちという側面もありますexitfare-induction.net。
こうした背景から、ホテル企業にとって若手人材の確保と離職防止は喫緊の経営課題となっています。
高齢層・シニアの活用
人手不足を補うため、50代以上のシニア層を積極採用する動きも広がっています。
ある調査では「既にシニア人材を採用している」宿泊施設が全体の60.9%に上ったとの結果がありprtimes.jp、
約6割のホテル・旅館が定年退職者やシルバー人材を活用していることがわかりました。
評価される点は「豊富な経験や接客スキル」「仕事への意欲が高い」といった部分で、
特に旅館の仲居役や観光案内役などでベテラン世代が頼りにされています。
一方で課題もあり、体力面での不安(重労働や夜勤は難しい)、
ITスキル不足(若者ほどデジタル機器に慣れていない)などから、
任せられる業務に限りがあるとの声もありますprtimes.jp。
また雇用形態も短時間パートや嘱託が中心で、人手不足解消の決定打にはなりにくい面があります。
それでも「経験豊富でまじめ」なシニア層は戦力になるとの評価は高く、今後も宿泊業でシニア採用は拡大すると見られます。
特にフロントや受付業務では、落ち着いた接客ができる中高年スタッフが重宝されているほか、
清掃業務でも地元のシニア層を雇用して長く勤めてもらう例があります。
女性・主婦層の参入
若年男性だけでなく女性や主婦層の雇用も注目されています。
宿泊業は24時間体制のため育児との両立が難しく、出産を機に離職する女性も多い業界でしたkankokeizai.com。
しかし近年、在宅勤務等は難しいまでもシフトの柔軟化や週3勤務など多様な働き方を認めるホテルも増え、
地元の主婦やママさん人材に来てもらう動きがあります。
また外国人を指導する立場としてベテラン女性が活躍するケースもあります。
今後、若者だけに頼らず幅広い年齢層から人材を集めることが、人手不足解消の一つのカギとなるでしょう。
宿泊業で離職率が高い理由と採用が難航する背景
宿泊業の高離職率
前述のようにホテル・旅館業界は離職率が高く定着しにくい産業です。
その背景には、労働環境・待遇面の厳しさが深く関係しています。
主な要因を整理すると以下の通りです。
- 低賃金・長時間労働: 宿泊業の平均賃金水準は全産業平均より低く、ボーナスなども含め収入面の魅力が乏しい傾向にありますglobal-saponet.mgl.mynavi.jp。加えて残業や深夜勤務が発生しやすく、慢性的な長時間労働になりがちです。他業種に比べ有給休暇の取得率も最低(49.1%)でglobal-saponet.mgl.mynavi.jp、十分な休息が取りづらいことから「割に合わない」という理由で辞めてしまう人が後を絶ちません。
- シフト勤務の負担: 早朝から深夜まで営業時間が及ぶホテルでは交替制勤務が避けられず、不規則な生活リズムになりますglobal-saponet.mgl.mynavi.jp。夜勤明けや長時間拘束による疲労が溜まりやすく、体調や私生活に支障を来して退職を考える従業員もいます。特に他業界のような土日固定休が取りにくい点は、若手に敬遠される一因です。
- ライフイベントとの両立困難: 結婚・出産・育児・介護などライフイベントを迎えた際に、宿泊業は柔軟な働き方がしにくいと言われます。深夜シフトや転勤を伴う働き方は家庭との両立が難しく、優秀な人材でも30代で離職するケースが多々ありますkankokeizai.com。育児休業制度等は整備されつつありますが、現場の人手不足ゆえに長期休暇の取得が難しい職場もあり、結果として女性や中堅社員の離職が増え人材が定着しない悪循環につながっています。
以上のような要因が重なり、宿泊業界は慢性的な人材流出に悩まされています。
この高離職率そのものが人手不足に拍車をかける要因であり、
採用してもすぐ辞めてしまうため常に人材が足りない状況が続くという構図ですmot-net.commot-net.com。
企業は離職防止のため労働条件の改善に努めていますが、構造的な課題の解決には時間を要しています。
都市集中と地方の応募難
前章でも触れましたが、日本人労働者の動向として都市部への人口集中も地方宿泊業の苦境を招いています。地方圏では若者が地元に残らず都市に出てしまうため、ホテル・旅館の地元採用が極めて困難です。
「地元で働き手が見つからないので外国人に頼るしかない」という地方旅館経営者の声も多く聞かれます。
また求人募集をかけても「応募ゼロ」が珍しくなく、人材紹介会社に頼らざるを得ないケースもあります。
対して東京や大阪など都市圏では、求人自体は集まりやすいものの競合他社も多いため優秀な人材の奪い合いになります。
結局のところ、日本全体で見れば人材が都市部の有名ホテルに偏り、地方・中小規模施設ほど採用難という傾向が強まっていますasahi.com。
待遇格差の問題
加えて、待遇面での業界内格差も応募難の原因となります。
先述のように宿泊業の賃金水準は低めですが、その中でも外資系高級ホテルなどは比較的高給で、
逆に小規模旅館では最低賃金に近いところもあります。
当然ながら条件の良い企業に応募が集中し、そうでない所には来ません。
最近ではインバウンド人気でホテル客室単価が上昇しておりtdb.co.jp、
経営的には好調なはずなのに人件費には反映されないという声も。
業界全体で待遇改善が進まないと、他業界(飲食や物流など)の方が賃金が良いためそちらへ人材が流れてしまいます。
実際、同じ外国人材の獲得競争でも宿泊業より外食業の方が給与水準が高く人気という指摘もありtravelvision.jp、ホテル業界は賃金面でも競争力強化が求められています。
要約すると
「きつい・安い・休めない」という従来からのイメージが根強く、
若者から敬遠→人手不足→既存社員の業務過多→さらに離職…
という負のスパイラルが応募難・定着難の根本要因となっていますmot-net.com。
待遇改善と働きやすい環境づくりなしに人材確保は難しいという点は、人日本人・外国人を問わず共通の課題と言えるでしょう。
外国人採用に影響するインバウンド需要と政府支援施策
観光需要の回復と人材不足
2023年以降、訪日外国人旅行は急速に復活しつつあります。
観光庁の統計では、2024年4月の宿泊者数は延べ5190万人泊と前年同月比+10.1%(うち外国人は+46.9%で1450万人泊)と大きく増加しましたtdb.co.jp。
また円安も追い風となり、日本への旅行は割安感から世界的に人気が高まっていますtdb.co.jp。
その結果、都市圏・観光地のホテルは軒並み高稼働・客室単価上昇となり、
業界はコロナ前の水準以上の好景気を享受しつつありますtdb.co.jp。
政府も「観光立国」の旗印のもと2025年に訪日客6000万人という野心的目標を掲げhotelbank.jp、
各種ビザ緩和やプロモーション支援を進めています。
このインバウンド特需とも言える状況はホテル経営には追い風ですが、その一方でサービス提供の担い手不足という新たなボトルネックを生じさせました。
つまり、お客様は増えているのにスタッフが足りず受け入れきれないという問題ですtdb.co.jp。
実際、人手不足のため客室稼働率に意図的に上限を設けて営業したり、
レストランの営業時間を短縮する宿泊施設もありますtdb.co.jp。
旺盛な需要を十分取り込めず機会損失が発生しているケースもあるため、
人材不足はせっかくのインバウンド需要拡大を阻む要因ともなっています。
宿泊料金上昇と人件費・採用コストの関係
需要増によりホテルの平均客室料金(ADR)は主要都市で大幅に上昇しました。
例えば東京や京都ではコロナ前比で20~30%高い料金設定となっている例もあります。
このように収益環境が改善したことで、本来であれば従業員給与を上げる余力も生まれているはずです。
実際、一部の高級ホテルではインフレ手当やベースアップに踏み切ったところもあります。
しかし業界全体で見ると、人件費の増額は限定的で、依然として賃金水準の低さが人材確保のネックになっていますtravelvision.jp。
前述のように、今後宿泊業界が必要な人材を獲得するには「給与水準を上げるか、日本語要件を下げるか」のどちらかが不可欠との指摘もありますtravelvision.jp。
つまり待遇改善なしに人手不足を解消するのは難しく、旺盛な観光需要を人材投資に結び付けられるかが課題です。
政府・行政の支援施策
人手不足対応に関して政府もいくつかの支援策を講じています。
まず外国人材の受け入れ制度として、2019年に「特定技能制度」を創設し宿泊業もその対象分野となりました。
これにより、一定の試験に合格した外国人がホテルで就労できるようになり、制度開始から5年で徐々に定着が進んでいますtravelvision.jp。
さらに技能実習制度でも2018年から旅館ホテル職種が追加され、海外から研修生を受け入れて育成する道も開かれました。
政府は他にも、観光庁を通じて宿泊業の人材確保支援策を展開しています。
例えば各地でマッチングイベントやセミナーの開催mlit.go.jp、
特定技能制度の周知と定着促進、
さらに雇用環境整備に対する補助金などです。
実際、「観光地・観光産業における人材不足対策事業」として2025年度も予算措置が取られ、
1施設あたり最大500万円の補助金交付(業務効率化ツール導入や人材育成費用への補助)が予定されていますfunaisoken.co.jp。
また厚生労働省系の助成金でも、外国人雇用企業向けの研修助成などが利用可能ですguidablejobs.jp。
このような公的支援を活用することで、企業側の負担を軽減し人材確保を後押ししようという動きがありますguidablejobs.jp。
総じて
インバウンド需要増はホテル業界にとってチャンスである一方、
人手不足という内部要因がそれを十分享受できないリスクとなっています。
政府の制度整備や支援策もうまく活用しつつ、業界全体で労働環境を改善していくことが必要でしょう。
国も観光産業を支える人材基盤強化を重要視しており、
企業側もそれに応える形で外国人材の積極登用や生産性向上投資を進めることが求められています。
外国人スタッフの適性・英語対応・夜勤への育成可能性
多言語対応・異文化理解力
外国人スタッフ最大の強みは、やはり語学力と異文化対応力です。
英語はもちろん、中国語・韓国語など母語を活かしてインバウンド客への対応品質を高めてくれますhotelbank.jp。
例えば海外からの宿泊客が増加する中、フロントで外国人スタッフが母語対応することで顧客満足度が向上したというホテルもあります。
また興味深いことに、外国人スタッフによる接客は日本人客からも高評価を得るケースがありますmlit.go.jp。
彼らの真摯で前向きな仕事ぶりに触れて「一生懸命なおもてなしが伝わる」と感じる日本人ゲストもおり、
外国人=サービス品質が劣るという偏見は払拭されつつありますmlit.go.jp。
むしろ多文化共生の職場は社内の刺激にもなり、モチベーション向上に寄与するという調査結果もありますguidablejobs.jp。
このように語学面・態度面で優秀な外国人材は、日本人と変わらない戦力として活躍できるのですmlit.go.jp。
夜勤・シフトへの適性
一般に深夜帯の業務は敬遠されがちですが、外国人スタッフの中には比較的順応している例もあります。
母国に家族を残して働きに来ているケースでは
「稼げるうちは頑張りたい」と深夜手当を歓迎する人もいます。
コンビニ等で深夜シフトを外国人が多く担っているのと同様、
ホテルでも深夜フロントや警備のポジションに外国人が配置されることがあります。
例えば24時間対応のフロントでは、日本語による高度な案内が少ない深夜帯は外国人スタッフ単独で任せ、
早朝以降の日本人客対応が増える時間帯に日本人社員と交代する、といった運用も可能でしょう。
もちろん人によりますが、「夜勤専従でも構わない」という意向の外国人もおり、
日本人が嫌がるシフトをカバーできる点は実務上のメリットです。
ただし健康管理や防犯面の教育は重要で、言語の壁で緊急時対応が遅れないよう英語対応スタッフに限定するなど工夫も必要です。
育成の可能性
外国人スタッフは「最初から完璧」でなくとも、育成次第で戦力化できる余地があります。
例えば日本語が十分でないスタッフでも、まずバックヤード業務(裏方)で経験を積みつつ日本語力を磨き、
その後フロントに配置換えするという育成計画も考えられますtravelvision.jp。
杠氏(マイナビグローバル社長)は今後の宿泊業採用は
「フロント等日本語力要の業務は高度外国人材(技人国ビザ)で、
その他の雑務・マルチタスクは特定技能で採用し、入社後に日本語研修を経てフロントにシフト」
という流れになると予想していますtravelvision.jp。
まさに適材適所と教育を組み合わせたモデルで、これは人材の能力開発により活躍領域を広げる戦略です。
事実、特定技能で来た外国人材が働きながら日本語学校に通い、
数年後にフロント業務に挑戦した例もありますmlit.go.jp。
企業側が育成の意識を持ち、役割期待を共有してキャリア形成を支援すれば、
外国人材も力を発揮し定着につながると国の調査でも報告されていますmlit.go.jp。
彼らは勤勉で向上心のある人が多く、適切に研修機会を与えればリーダーやトレーナー役まで担えるようになりますmlit.go.jp。
重要なのは、日本人社員と同様に長所・強みを見極めて配置し、段階的に責任ある仕事を任せていくことですmlit.go.jp。
そうすれば、将来的に外国人が管理職や専門職として組織を支える人材へと成長していく可能性は十分にあります。
雇用期間・定着率・待遇の影響(寮、手当、採用プロセス~入社まで)
外国人スタッフの平均雇用期間
外国人の定着を考える上で、まず在留資格による在留期間の制約があります。
例えば技能実習生は最長3年(条件により5年まで延長可)、
特定技能1号は最長5年(2号に変更でさらに5年)といった制限があり、
それを過ぎると原則帰国となります。
一方で、技術・人文知識・国際業務や永住者・定住者などの資格を持つ人材は期間の上限なく就労可能ですhotelbank.jp。
したがって、採用する外国人のビザ種別によって雇用可能期間は異なることを念頭に置く必要があります。
受け入れ環境と定着
寮や社宅の有無は外国人定着に大きく影響します。
特に地方リゾート地では社員寮を完備し、光熱費も無料とするなど生活面の不安を取り除く工夫をしている施設が多いですguidablejobs.jp。
住居が安定すると余計な出費や通勤ストレスがなくなり、仕事に集中しやすくなります。
また食事提供(社員食堂)や交通費支給も基本ですが、
遠方出身の外国人には年に一度の帰国補助や通信費補助などを用意する企業もあります。
給与以外にこうした手当が充実していると、「この会社で働き続けたい」という気持ちにつながります。
さらに、前述したようにキャリアパスの提示や研修も定着率アップには有効ですmlit.go.jp。
上司から定期的にフィードバックをもらえたり、昇進のチャンスがあると感じられる環境ではモチベーション高く働けます。
逆に言葉の壁から孤立してしまうと早期離職につながりかねません。
そのため、外国人が職場で孤立しない仕組み(日本人社員との交流会、メンター制度、困り事相談窓口の設置など)も重要とされていますmlit.go.jp。
例えば寮での共同炊事イベントや周辺観光に連れ出す取り組みをするホテルもあり、
そうした温かい職場風土が結果的に長く働いてもらうことにつながっていますmlit.go.jp。
採用から入社までのタイムライン
外国人採用のプロセスは日本人新卒のように一斉入社ではないため、
内定から就労開始までの流れを丁寧に設計する必要があります。
海外在住者を採用した場合、就労ビザの手続きに2~3か月要するのが一般的です。
採用企業は在留資格認定証明書(COE)の申請を法務省に行い、許可後に本人がビザ発給を受けて来日するという段取りになります。
この間に業務マニュアルの多言語化や、住居手配、空港出迎え準備など受け入れ準備を進めます。
また入社日直後から即戦力とは限らないため、研修期間も考慮しましょう。
例えば最初の2週間はオリエンテーションと日本語研修に充て、その後現場配属というケースもあります。
留学生や国内在住の転職者を採用する場合はビザ変更手続き(資格外活動→就労ビザなど)を経て、
1~2か月程度で入社可能です。
いずれにせよ、採用内定から実際に働き始めるまでタイムラグがあるため、
繁忙期に間に合うよう逆算して採用活動を行う必要があります。
内定後から入社日までフォローを怠ると、他社に行ってしまうリスクもあるので、
定期的に連絡して不安を解消してあげると良いでしょう。
たとえば内定者向けにオンライン日本語講座を提供したり、
社内の外国人社員と交流できるチャットグループに招待するといった工夫も見られます。
待遇の差が与える影響
最後に待遇面について補足します。
外国人スタッフの間でも「このホテルは働きやすい」「待遇が良い」という評判は口コミで広がります。
寮完備・残業代100%支給・昇給あり、といった好条件の職場には同僚紹介で新たな人材が集まるという好循環が生まれますguidablejobs.jp。
実際、社員の友人紹介制度(紹介者に報奨金)を設けて外国人ネットワークから追加採用に成功した例もありますguidablejobs.jp。
逆に、約束した待遇が守られなかったり差別的扱いを受けたりすると不信感から早期退職に直結します。
日本人以上に外国人は勤め先の評判をSNS等で共有することも多いため、一人ひとりの待遇・処遇を適正にすることが次の人材確保にも影響します。
言い換えれば、外国人スタッフにとっても「働きがいのある職場」を作ることが、長期定着と新規採用双方にプラスに働くのです。
未経験者・留学生の活用とそのポテンシャル
未経験層(他業界出身者や新卒)の可能性
慢性的な人手不足を補うには、ホテル業未経験の人材をどれだけ取り込めるかも重要です。
特に外国人の場合、日本での就業経験がない人でも潜在的に有望な人材が多く存在します。
例えば来日したばかりの留学生や、日本の接客業務は未経験でも本国でサービス業経験がある人などです。
彼らは最初は戸惑うこともありますが、現場でのOJTや先輩社員のフォローにより急速に成長するケースが多いと報告されていますmlit.go.jp。
実際、「未経験だったが数か月で即戦力に育った」という声は各地で聞かれます。
特にホスピタリティ業務は本質的に人との関わり方次第で伸びる部分が大きく、
コミュニケーション能力が高い外国人であれば後天的にいくらでもスキルアップ可能です。
大事なのは、未経験だからと敬遠せずチャレンジの機会を与えることです。
留学生のアルバイト・正社員登用: 日本には約30万人の外国人留学生が在籍していますが、
彼らは貴重な労働力です。
資格外活動の許可により週28時間までアルバイトが可能なため、
ホテルのフロントやレストランで留学生アルバイトを受け入れる例が増えています。
特に観光系や日本語学校の留学生は接客業への関心も高く、
実際に働いてみて宿泊業への興味が高まったという調査結果もあります。
あるアンケートでは、宿泊業未経験でお手伝い的に旅館で働いた人のうち67.6%が「関心が高まった」と回答し、「また働きたい」が79.6%に上ったとの報告がありますprtimes.jpprtimes.jp。
これは一時的なアルバイト経験が将来の観光人材発掘につながる可能性を示しています。
実際、そのまま卒業後に正社員として採用された留学生も多数います。
ホテル側にとって留学生アルバイトは即戦力かつ採用候補の見極め期間として機能し、
本人にとっても就職前に会社を知る機会となるため、双方にメリットがあります。
今後はインターンシップやスポットワークを通じて、未経験の若者が宿泊業に触れる機会を増やし、
人材裾野を広げることが重要でしょう。
ポテンシャルの引き出し
未経験者でも潜在能力の高い人は多く、適切な配置と教育で才能を開花させることができます。
例えば「人と話すのが好き」「世話好き」という性格の人は接客業に向いており、
外国人であってもまずは笑顔と基本マナーを教えれば十分にお客様に喜ばれる存在になれます。
また異業種から転職してきた外国人は前職のスキル(ITスキル、語学、料理の腕前など)を活かし、
ホテル内の業務改善に貢献することもあります。
実際、あるベトナム出身スタッフはエンジニア経験を買われてホテルのIT担当に抜擢され、
予約システムの効率化を実現した例もあります。
こうした例から学べるのは、採用段階で経験だけを重視せず、
人柄・意欲・他分野のスキルに注目することの大切さです。
未経験だから戦力化に時間がかかると考えがちですが、モチベーションの高い人材であれば飲み込みも早く、
かえって独自の発想でサービスを向上させる場合もあります。
受け入れ時のポイント
未経験者を受け入れる際は、最初の配属業務や教育担当者の選定が肝心です。
例えばいきなり難しい業務を任せず、簡単な業務からスタートさせ成功体験を積ませること、
分からないことを気軽に聞ける先輩(メンター)を付けることなどが有効ですmlit.go.jp。
また評価制度も日本人ベテランと同じ基準では酷なので、
習熟度に応じて段階的な目標を設定すると良いでしょう。
そうすれば未経験者でも萎縮せず伸び伸びと力を発揮でき、
結果としてポテンシャルを十分に引き出すことができます。
外国人採用時に必要な日本語スキルと確認ポイント
日本語能力の重要性
ホテル業で働く上で日本語力は欠かせないスキルであることは言うまでもありません。
ただし求められるレベルは職種や役割によって大きく異なります。
一般に、日本語能力を測る指標として日本語能力試験(JLPT)の級が用いられることが多く、
N1(最難関)~N5(初級)の5段階評価ですarticle.tenjee.com。
ホテルの求人では「N3以上」を応募条件とする場合が多く、
日常会話に支障がないレベルを求めるのが一般的ですarticle.tenjee.com。
N3は「ある程度の敬語を含む日常会話が理解できる」程度で、接客でも基本的な対応は可能とされています。ただ、高級ホテルや旅館ではN2レベル(より高度な敬語や複雑な会話が理解できる)以上を求める傾向が強いとも言われますtravelvision.jp。
実際、介護業や外食業では応募条件がN3程度が主流なのに対し、
宿泊業ではより高いN2を求める傾向にあるとのデータがありますtravelvision.jp。
一方で、特定技能ビザで来日するためにはN4相当でも可能なため、
そのミスマッチが課題とも指摘されていますtravelvision.jp。
つまり、制度上は簡単な日本語で来られる人材でも、
ホテル側が高い語学力を期待しすぎると採用が進まないという問題です。
確認すべきポイント
外国人を採用する際には、日本語の会話力と読み書き力の両面を確認しましょう。
具体的には以下のような項目が考えられます。
- 会話力: お客様対応に必要な口頭コミュニケーション能力。
敬語の使い方、電話応対ができるか、緊急時に適切な報告連絡ができるかなど。
面接時にロールプレイで日本語接客させてみると実力を把握できます。
また他スタッフとの意思疎通(日本語での日常会話)が問題ないかも重要です。 - 聴解力: 日本語の指示を正しく聞き取れるか。
バックヤードで上司の指示や朝礼の内容を理解できないと業務に支障が出ます。
これも面接時の質疑でどこまで理解しているか観察します。
場合によっては専門用語を交えて反応を見ることもあります。 - 読解力: 業務マニュアル、掲示物、予約システム画面、日本人客の氏名(漢字)などを読み取る力。
読めない漢字が多すぎるとフロントでのチェックイン手続き等に時間がかかる恐れがあります。
対策として、ひらがな・カタカナが読めるかは最低限確認しますguidablejobs.jp。
また住所や氏名の漢字をメモから写せる程度の読み書きは必要でしょう。
簡単な筆記テスト(例:「田中太郎様 2名 朝食付き」の予約票を読ませる)でチェックすることも考えられます。 - 文章作成力: 業務日報の記入や社内メール作成など書く能力も確認します。
とはいえ高度なビジネス文章までは求めにくいので、例えば簡単な自己紹介文を書かせて文法ミスの程度を見る程度で良いでしょう。
最近は翻訳ツールもあるため、文章力は会話力ほど厳しく見る必要はありませんが、
漢字交じりの文を読めるかは重要です。
基準設定の工夫
求人票に記載する日本語レベル基準は、応募数と人材クオリティを左右するため慎重に検討します。
高すぎる基準は応募者を狭め、低すぎると現場負担が増すからです。
ポイントは、職種ごとに現実的な基準を設けることです。
例えば、フロント担当なら「N2以上(またはビジネス会話レベル)を目安。敬語でスムーズな接客ができること。」
レストランホールなら「簡単な注文のやり取りができれば可(N3程度)」、
清掃スタッフなら「作業指示が理解できれば可(会話に不安がある場合は翻訳アプリ使用可)」
といった具合です。
また前述の事例のように、あえて「英語・中国語など話せる方歓迎(日本語初級でも可)」と打ち出して多言語人材を集める方法もありますguidablejobs.jp。
実際、「日本語は初歩レベルでもOK」とした求人に50名の応募が集まり、
多言語対応可能な若手人材を獲得できた例もありますguidablejobs.jp。
そのホテルでは日本語要件を下げた代わりに、日本人スタッフとの複数名体制で接客させるなど工夫して業務を回しています。
このように求める日本語力を柔軟に設定することで人材の幅を広げることも可能です。
確認方法
採用プロセスでは、日本語力は書類選考→面接→筆記/適性テストの各段階でチェックできます。
履歴書の日本語の内容やJLPT資格有無をまず確認し、オンライン適性テストで読解力・文法力を測定、
最後に面接で実際の会話力を見ると総合判断しやすいです。
JLPTの級取得者であっても実際話してみるとコミュニケーションが難しい場合もあるので、
面接時の会話評価を重視すべきでしょう。
逆に資格がなくても現場で通用する人もいるので、偏見を持たず実力本位で判断することが大事です。
基準未達の場合の対応
もし優秀な人材だが日本語だけ基準未達という場合、
採用を見送るのではなく研修前提で採用する選択肢もあります。
例えば入社前または入社直後に日本語学校や社内教育で短期集中トレーニングを実施することで、
実務に必要な言い回しを覚えてもらうことができます。
費用はかかりますが、そこで定着して長く活躍してもらえれば十分回収できる投資です。
特に特定技能の外国人はN4レベルで来日するため、
ホテル側で追加教育してN3相当に引き上げる取り組みも行われていますtravelvision.jp。
今後、宿泊業界全体で見ると「求める日本語レベルを多少下げてでも人材確保」へシフトすることが予想されますtravelvision.jp。
実際そのような提言も専門家からなされており、各社が対応を迫られていますtravelvision.jp。
ホテル業界における外国人採用の総まとめと今後の展望
以上、ホテル業界における外国人採用動向を人手不足の背景から具体策まで総合的に分析しました。
人材不足という課題に対し、外国人材の登用はもはや避けては通れない戦略となっています。
ただし成功させるには単に人数を埋めるだけでなく、
適切な職種配置、十分なコミュニケーション、働きやすい環境整備が欠かせません。
幸い、多言語対応や旺盛な勤労意欲など外国人スタッフならではの強みは大きく、
育成次第では将来の中核人材にもなり得ます。
政府の制度や支援も追い風となっており、
今後は外国人と日本人が協働してホテルのサービス水準を向上させていく時代となるでしょう。
人事担当・経営層におかれては、ここで挙げた課題と解決策を参考に、
自社の採用・定着戦略を再点検いただければ幸いです。
人材多様化によって初めて、真の意味で「おもてなし」の裾野が広がる――
ホテル業界が直面する転換期を乗り越える鍵は、
外国人材の可能性を最大限に引き出すことに他なりません。
参考文献・情報ソース(本文中に【】で示した出典):
- 帝国データバンク: 「旅館・ホテル業界の人手不足動向」(2023~2025年)【7】【29】 他
- 外国人採用サポネット(マイナビ): 宿泊業の人材不足現状と原因【10】、外国人労働者数の推移【40】 他
- HotelBank: 「ホテル業界における外国人材の必要性と現状」(2025年)【19】 他
- トラベルビジョン: 「宿泊業の外国人材求人急増と課題」(2024年3月)【45】
- MOT/ブログ: 「宿泊業界の人手不足の原因と対策」(2024年)【32】 他
- PR Times: 各種調査リリース(観光庁・おてつたび 等)【38】
- 観光庁資料: 「宿泊業における外国人材受入れ成功要因」【36】 他
- Guidable社ブログ: 外国人採用事例(ホテル業界)【23】 他
- その他、厚生労働省データ、業界ニュースサイト【35】等.