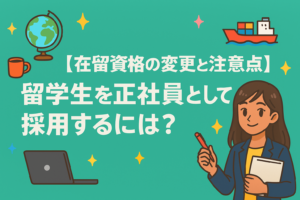外国人採用に使える助成金まとめ|活用できる支援制度と実践ポイント
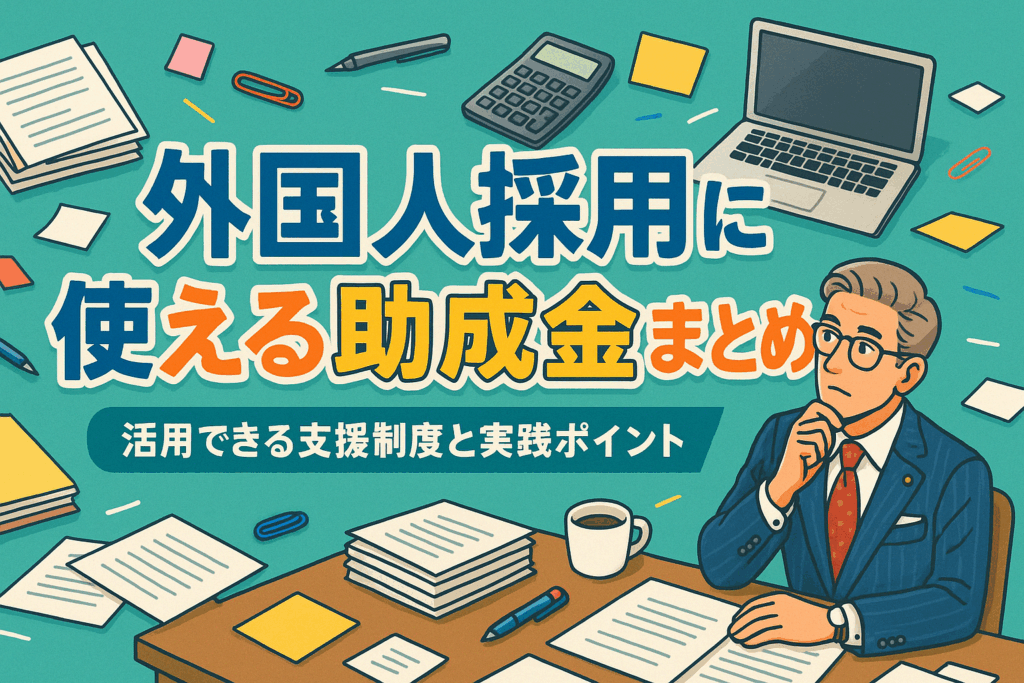

「外国人を採用してみたいけど、コストや手続きが不安でなかなか踏み出せない…」
そんな風に感じていませんか?
実は、外国人の雇用を支援する補助金や助成金制度がいくつも用意されています。
制度の仕組みを知り、うまく活用することで、
採用コストを抑えながら、優秀な人材を迎え入れることができるかもしれません。
ただし、
「外国人=自動的に使える補助金がある」わけではないので、
制度の内容と適用条件をしっかり理解しておくことが大切です。
この記事では、
外国人採用を検討中の中小企業の経営者・人事担当者向けに、
- 外国人採用に使える主な助成金制度の一覧
- 活用時の注意点と申請のポイント
- 採用手法別のコスト比較
- 現場での実例を交えた活用のヒント
などを、わかりやすく整理してお届けします。
💡 採用にかかるコストを少しでも抑えたい方、
制度の存在を知らずに損をしたくない方に、特に役立つ内容です。
目次
外国人採用で使える助成金・補助金とは?
▷ 助成金と補助金の違いをシンプルに整理
「助成金」と「補助金」って、似たような言葉に感じてしまいますが、
実はこの2つ、制度の背景や仕組みが少し異なります。
| 区分 | 助成金 | 補助金 |
|---|---|---|
| 管轄 | 厚生労働省 | 経済産業省・自治体など |
| 特徴 | 雇用や人材育成の目的で支給される | 設備投資や事業促進の支援が多い |
| 審査 | 条件を満たせば原則支給される | 応募多数の場合は採択制 |
| 支給方法 | 後払い(実績ベース) | 後払い or 前払い(制度により異なる) |
| 申請難易度 | 比較的わかりやすい | 計画書・審査が必要な場合が多い |
📝補足:外国人の採用においては「助成金(雇用系)」がメインとなることが多く、
特に厚生労働省の雇用関係助成金が代表的です。
💡参考リンク:厚生労働省|雇用関係助成金の概要
外国人採用で「使える可能性のある」制度とは?
「外国人を採用する」と言っても、活用できる制度はケースバイケースです。
代表的なものを分類して整理します。
| 分類 | 制度名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 雇用関係助成金 | トライアル雇用助成金 | 外国人含む未経験者の試用雇用で活用可能 |
| 雇用関係助成金 | 特定求職者雇用開発助成金 | 生活保護受給者や母子家庭、外国人などが対象になるケースあり |
| 雇用関係助成金 | キャリアアップ助成金 | 有期雇用 → 正社員化で支給される可能性あり |
| 育成支援 | 人材開発支援助成金 | 外国人社員向けOJT/Off-JT研修に活用可 |
| 地方自治体系 | 各自治体独自の助成金 | 通訳配置費・語学研修費などに利用可(例:東京都、愛知県) |
📝補足:「外国人だから使える」というより、「外国人でも対象になる制度がある」と考えましょう。
制度の対象になる雇用形態・条件の概要
制度ごとに異なりますが、よくある共通条件をまとめます。
✅ よくある主な条件:
- 社会保険・雇用保険の加入が必要(例:週20時間以上勤務など)
- 雇用契約期間が6ヶ月以上
- 対象職種や業務内容が正しくマッチしている
- 助成金対象になる「在留資格」での就労である(例:特定技能、技術・人文知識・国際業務 など)
📝注意:
「留学」ビザのままアルバイトとして雇用しても、助成金の対象にはなりません。
変更手続きを完了し、「就労可能な在留資格」であることが前提になります。
よくある誤解:「外国人だから使える」わけではない
これは特に多い誤解です。
✅ よくあるNGパターン:
- 「外国人を雇ったから自動的に助成金がもらえる」と思っている
- 対象要件を調べずに採用してしまい、後から「適用外」だと知る
- ビザの種類や雇用形態を確認しないまま申請しようとする
助成金はあくまで「特定の目的・条件を満たした雇用」への支援制度です。
対象にならないケースも多いため、事前に確認・準備しておくことが大切です。
申請に必要なタイミングと流れの全体像
助成金の多くは「採用前後の手続き」が肝になります。
申請までの基本的な流れ(例:トライアル雇用助成金)
- 採用前にハローワーク等で求人申請を出す
- トライアル雇用として採用(契約書など整備)
- 対象者の就労開始
- 一定期間経過後に、必要書類を添えて申請
- 書類審査 → 支給
📌重要なのは、「後からまとめて出せばOK」ではないということ。
申請には“事前手続き”が必要な制度がほとんどです。
📎【ここに挿入】図:「助成金申請の流れ(タイムライン形式)」
🔚 この章のまとめ
- 助成金と補助金の違いを理解しておくことが第一歩
- 外国人だから使えるというより、「外国人にも使える制度」がある
- 対象になるかどうかは、雇用形態・条件・タイミング次第
- 「知らずに損した」「出したのに通らなかった」を防ぐには、採用前の確認が重要!
主な制度① 厚生労働省系の雇用関係助成金
外国人を雇用する際に活用できる可能性がある助成金の中でも、
厚生労働省が所管する「雇用関係助成金」は中小企業にとって特に身近な制度です。
ここでは、外国人採用でも活用事例の多い主要な3つの助成金を紹介し、
それぞれの特徴や注意点をまとめます。
▷ トライアル雇用助成金(外国人も対象)
「まずはお試しで雇ってみたい」という企業に向いている制度です。
求職者の職業経験などに不安がある場合、
一定期間(原則3ヶ月)試用雇用を行った企業に、1人あたり月4万円(最長3ヶ月・最大12万円)が支給されます。
外国人も条件を満たせば対象になります(ハローワーク等からの紹介が必要)。
主な要件:
- ハローワーク等から紹介された求職者であること
- 採用時に雇用保険に加入すること
- 過去に同じ人物を雇っていないこと
注意点:
申請のタイミングを逃すと支給されません。雇用開始前に準備を。
▷ 特定求職者雇用開発助成金
(生活困窮者・障害者・母子家庭の母など)
こちらは、「就職が困難な方」に該当する外国人(例えば生活保護を受けていた方や難民認定者など)を継続的に雇用する場合に活用できます。
正社員採用で最大60万円(中小企業の場合)、パートタイムなど一定の要件を満たせば最大30万円が支給されます。
主な要件:
- 対象者が厚労省の定める「特定求職者」に該当すること
- ハローワークなどの紹介による採用であること
- 継続雇用(6ヶ月以上)すること
注意点:
対象者の要件確認と、雇用開始前の申請準備がカギです。
▷ キャリアアップ助成金(有期→正社員化)
外国人の中には、最初は有期雇用契約で働き、実力を見てから正社員化するというケースもあります。
このとき、有期契約→正社員に転換した場合に使えるのがこの制度です。
中小企業なら1人あたり最大57万円の助成金が支給されます(条件を満たす場合は加算もあり)。
主な要件:
- 転換前の雇用契約期間が6ヶ月以上
- 転換後も継続的に雇用されていること
- 就業規則などに「転換制度」が明文化されていること
注意点:
就業規則の整備や、実際の転換手続きをきちんと記録しておくことが大事です。
▷ 対象者・企業・条件のポイント整理
| 制度名 | 対象となる雇用形態 | 外国人の対象可否 | 支給額の目安 |
|---|---|---|---|
| トライアル雇用助成金 | 試用的な有期雇用 | 可(紹介経由) | 月4万円×3ヶ月 |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 正社員または一定の有期雇用 | 可(条件あり) | 最大60万円 |
| キャリアアップ助成金 | 有期→正社員化 | 可 | 最大57万円(加算あり) |
▷ 書類不備や条件違反で「もらえない」事例も
実はこの種の助成金、申請すれば必ずもらえるわけではありません。
特に多いミスが以下のようなものです:
- 「雇用前に申請していなかった」
- 「対象者の条件をよく確認していなかった」
- 「提出書類の一部が不備だった」
- 「就業規則が未整備だった」
いずれも、制度の仕組みと運用の細かい部分まで理解していないと起こりがちです。
手続きが不安な場合は、社会保険労務士など専門家と連携するのが安心です。
主な制度② 人材育成・研修関連の助成金
外国人材を定着させるためには、採用後の育成体制がカギになります。
ただし、中小企業にとっては「研修コストが高い」「研修をどう組めばいいかわからない」といった悩みもつきもの。
そんなときに使えるのが、厚生労働省の「人材開発支援助成金」です。
▷ 人材開発支援助成金とは?
中小企業が社員に対して職業訓練(OJT・Off-JT)を実施する場合、その訓練にかかった賃金や費用の一部を補助してくれる制度です。
外国人社員も、もちろん対象になります。
たとえば…
- 日本語研修
- 接客マナー研修
- ITツールの使い方研修
- 外国人向けの社内ルール教育
こういった研修に助成金を活用できます。
▷ OJT・Off-JTに使える具体的な内容
| 項目 | 内容 | 支給例(中小企業) |
|---|---|---|
| OJT(職場内訓練) | 実務を通じて指導員が教える研修 | 指導員1人あたり月2万円(上限) |
| Off-JT(外部講師など) | 講座・セミナー等で行う座学研修 | 研修費用の45%補助+1時間あたり760円の賃金補助(上限あり) |
ポイント:
- 外部講座(日本語学校など)に通わせる費用も対象になる可能性があります。
- 社内研修でも、きちんと記録を取って設計すれば支給対象になります。
▷ どんな研修内容が対象になるのか?
助成対象になるには、以下のような「業務スキル向上を目的とした内容」が必要です。
✅対象になりやすい内容の例:
- 社内マニュアルに基づくOJT
- 日本語能力向上(業務上必要なレベル)
- 社会人マナー・ビジネスマナー研修
- 業界特有の知識やルール教育
- 接客・販売スキル
- IT・PCスキル
❌対象になりにくい例:
- レクリエーション目的のイベント
- 入社式・懇親会
- 専門性のない雑談ベースのミーティング
補足:
制度の利用には「研修計画書」や「受講記録」の提出が必要です。
事前に制度を確認した上で、助成金に“合わせた”形で研修設計をすることが重要です。
▷ 支給額の目安と申請の流れ
【支給額の一例(中小企業の場合)】
| 内容 | 支給額 |
|---|---|
| Off-JT訓練経費 | 費用の45%(上限30万円/人) |
| Off-JT中の賃金 | 1時間あたり760円(上限あり) |
| OJT訓練 | 指導員に月2万円(最大6ヶ月) |
【申請の流れ(ざっくり5ステップ)】
- 研修計画の作成(実施前)
- 労働局への「事前届出」
- 研修の実施・記録(写真、出席簿など)
- 研修終了後に申請書類を提出
- 書類審査を経て、助成金が振込
📌 つまずきやすいポイント:
→ 「事前届出を忘れていた」=不支給になることが多いので注意!
→ 研修内容の設計時点で、制度に詳しい専門家(社労士等)に相談するのがベストです。
▷ 「制度に合わせた」研修設計の重要性
助成金を“もらうために”研修を行うのではなく、
「必要な研修を、制度に合わせて設計する」という発想が大切です。
たとえば:
- もともと予定していた社内研修を、対象形式(Off-JT)に調整して費用の一部を助成対象にする
- 外部の日本語学校に依頼する場合、助成金対象の研修実施証明書を発行してくれる学校を選ぶ
このように、制度を上手に“利用しながら”定着支援も進めるのが理想です。
▷ 公式リンク・参考資料
- 【厚生労働省|人材開発支援助成金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000119335.html - 【厚労省 助成金検索ページ】
https://joseikin.mhlw.go.jp/
✅ この章のポイントまとめ
申請前に準備する書類とタイミングを間違えないことが最重要!
人材育成のコストも助成金でカバーできる
OJTや外部講座も対象になるが、制度に合わせた設計が必須
地域独自の補助制度にも注目
外国人材の採用・定着支援においては、国の助成金だけでなく、
各自治体が独自に実施している補助制度も存在します。
これらの制度は、地域の特性やニーズに応じて設計されており、
外国人材の受け入れを検討する中小企業にとって有益な支援となります。
▷ 東京都の「外国人介護従事者受入れ環境整備等事業」
東京都では、介護施設等が外国人留学生を雇用し、
学費等を支給する場合に、その経費の一部を補助する制度を実施しています。
主な支援内容:
- 学費支援:介護福祉士養成施設や日本語学校に通う留学生の学費等を支給する場合、その経費を補助。
- 居住費支援:令和6年度より、居住費の補助基準額が年額60万円に増額。
- 初期費用支援:入居に係る初期費用として5万円(一回限り)を補助対象に追加。
詳細は、東京都福祉保健財団の公式サイトをご参照ください。
▷ 愛知県・大阪府などの取り組み例
愛知県:
愛知県では、外国人介護人材の受け入れを促進するため、以下のような支援を行っています。
- 環境整備支援:介護現場での外国人材の就労環境整備にかかる経費の一部を補助。
- 現地採用活動支援:海外現地での外国人介護人材確保の取り組みに対する経費の一部を補助。
詳細は、愛知県の公式サイトをご確認ください。
大阪府:
大阪府では、外国人介護人材の受け入れ施設等に対して、以下のような支援を行っています。
- 環境整備支援:介護業務に従事する外国人介護人材が円滑に就労・定着できるよう、施設等が実施する事業に要する経費を補助。
詳細は、大阪府の公式サイトをご参照ください。
▷ 給与以外にもかかる「受け入れの準備費用」をサポートしてくれる制度も
外国人材を受け入れるとき、給与や研修費用だけでなく、
言語サポートや住まいの確保など、さまざまな準備や支援に費用がかかることがあります。
こうした“受け入れのための準備費用”をサポートしてくれる制度を用意している自治体もあります。
【支援内容の一例】
- 生活支援(住まいや日用品など)
→ アパートの初期費用、生活用品の支給、引っ越しの支援など、生活立ち上げに必要な支援。
例:愛知県では、外国人介護人材の住環境整備にかかる費用を補助。 - 通訳サポートの人材配置
→ 外国人スタッフと現場スタッフのコミュニケーションを円滑にするための通訳費用を支援。
例:宮崎県では「外国人コンシェルジュ」の配置を支援。 - 医療や行政の手続き支援
→ 医療通訳の派遣、多言語での生活案内資料など。
例:群馬県では医療機関への通訳ボランティア派遣を実施。
【制度の例とリンク】
✅ ここがポイント
- お金の支援だけでなく、“人”の支援(通訳・生活サポートなど)も含まれることが多い
- 実際の支給額や対象条件は自治体ごとに異なるため、早めの確認が大切
- 地方では「受け入れ支援に熱心な自治体」も増えており、活用できると企業側の負担が軽減される
このようなサポートを上手に活用することで、初期の受け入れにかかる手間や不安を減らすことが可能です。
助成金も含め、「会社に合った採用のかたち」を考える

「やっぱりハローワークが一番いいですか…。
費用も抑えられそうだし、助成金も使えるかもしれないし」
そんなふうに感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
実際、ハローワーク経由の採用は、助成金の対象になりやすいなどのメリットがあります。
ただその一方で、
「本当に必要な人材が集まるか」「定着して活躍してくれるか」という観点も見落とせません。
▷ 大切なのは、「助成金が出るか」ではなく「誰を、どう迎えるか」
助成金はありがたい制度ですが、あくまで採用を“後押し”してくれるものです。
目的はあくまでも「良い人材を迎えて、長く活躍してもらうこと」。
そのためには、特徴やサポート内容も踏まえて、
自社に合った採用方法を考えることが大切だと感じています。
▷ 採用チャネルごとの特徴を比べてみると…
| 採用手段 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| ハローワーク | 費用がかからず、助成金対象になるケースが多い | 時間をかけて、幅広い応募を集めたい場合 |
| 求人媒体 | 募集範囲は広がるが、掲載料が先に発生 | 認知度や求人内容に自信がある場合 |
| 外国人紹介会社 | 成果報酬型。ビザ確認やフォローも含む | はじめての外国人採用・即戦力を求めている場合 |
ハローワークはとても有用な選択肢ですが、
在留資格のチェックや入社後の生活サポートなど、自社で行う必要がある工程も多いため、体制とのバランスを見ておくと安心です。
▷ 実は「採用コスト」は、見えづらいところにこそある
求人広告費や紹介料だけが「採用コスト」ではありません。
以下のような“あとから効いてくるコスト”も存在します:
- 応募対応や面接調整にかかる人手・時間
- 入社後の教育にかけるリソース
- 早期離職による再募集・再教育の手間とロス
たとえば、初期費用が抑えられても、採用がうまくいかずに何度もやり直し…というケースでは、
結果として人件費や時間がかさむこともあります。
▷ 採用方法を「比較」ではなく「設計」する視点へ
だからこそ大事なのは、「うちにとって最適な採用手段って何だろう?」と考えること。
業種や職場環境、日本語レベルの必要度、社内体制によって、ベストな方法は違ってきます。
もし迷われている場合は、「求める人物像」や「育成・活躍まで含めた視点」で、
一度整理してみると方向性が見えてきやすいと思います。
✅ この章のまとめ
“見えないコスト”も含めて考えると、結果的に納得のいく採用ができる
助成金はあくまで後押しの道具。目的は「人材の活躍と定着」
採用方法にはそれぞれ特徴があるので、自社の状況と照らし合わせて選ぶ
✅この記事のまとめ|外国人採用に使える助成金のポイント

- 助成金と補助金の違いを理解しよう
→ 雇用関係なら「助成金」、設備投資などは「補助金」が中心。 - 「外国人=自動で助成金対象」ではない!
→ ビザ種類・雇用形態・申請タイミングが適用条件に合っていることが必須。 - 代表的な活用可能制度は以下の通り:
- トライアル雇用助成金(試用的雇用)
- 特定求職者雇用開発助成金(生活保護等の経験者)
- キャリアアップ助成金(有期→正社員)
- 人材開発支援助成金(研修・OJT支援) - 多くの制度は「採用前の準備」が必要!
→ 求人申請・研修計画・就業規則の整備などは事前に済ませておくこと。 - 地方自治体の独自支援も見逃さずにチェック
→ 住居費や通訳費など“受け入れ準備費用”をサポートしてくれる制度も多数。 - 助成金に頼りすぎない視点が大切
→ 「誰をどう迎えるか?」という採用設計の工夫が、最終的な成功につながります。
💡POINT:
「使える制度」を知ることは第一歩。
でも、最終的に大切なのは「人材の定着と活躍」。
助成金はその後押しとして、うまく活用していきましょう!