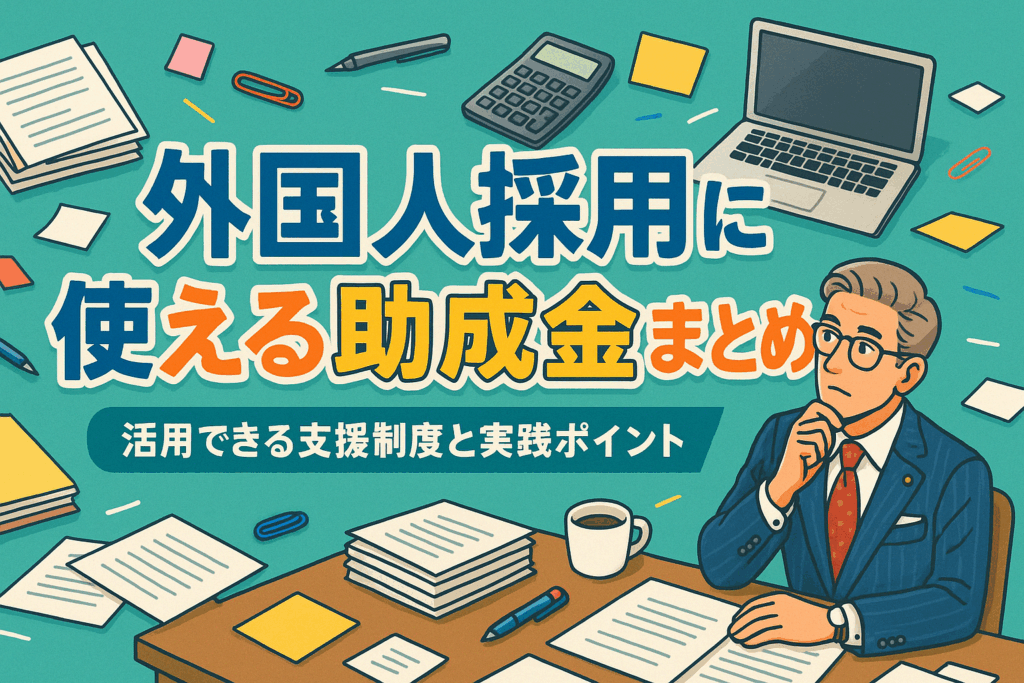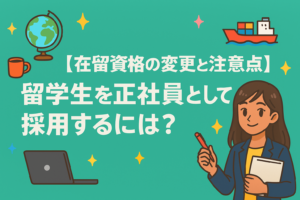外国人採用の基本が全部わかる!制度・ビザ・定着まで徹底解説
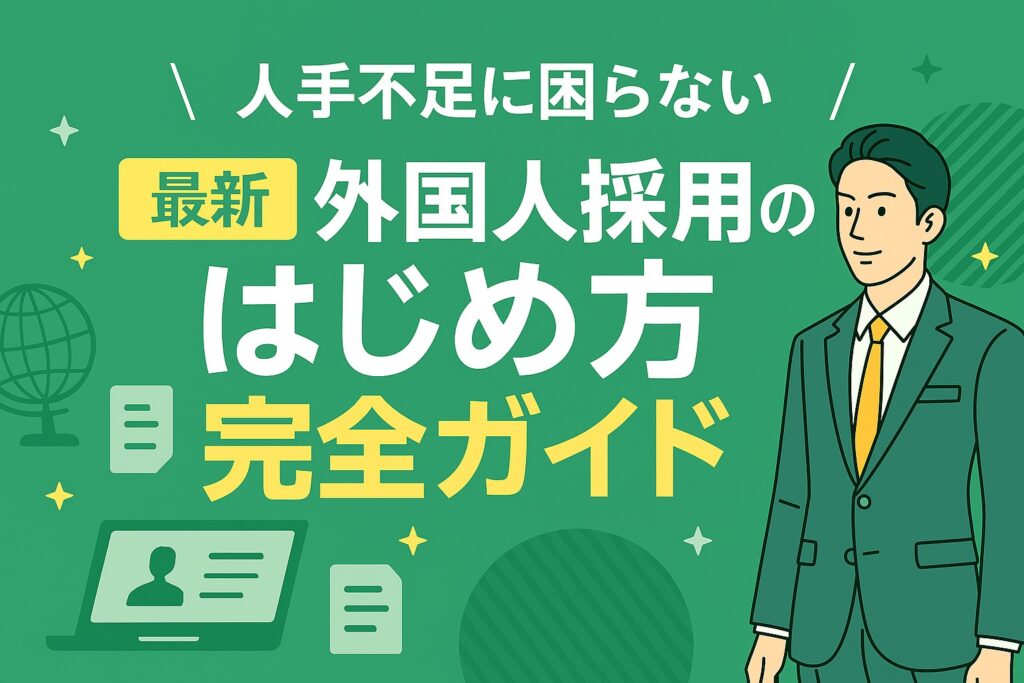
「優秀な人材を採用したいのに、なかなか出会えない」
「外国籍のハイキャリア人材も視野に入れたいが、制度や手続きが複雑で不安」
そんな課題を抱える企業の人事・経営者の方に向けて、
本記事では外国人採用の基本から、制度・ビザ・定着支援までをやさしく解説します。
この記事を読めば、
- 外国人採用の全体像がつかめる
- 必要な制度や手続きの流れがわかる
- 自社に合った採用方法のヒントが得られる
「はじめてでも安心して外国人採用をスタートできる」ための実践知識をまとめました。
制度の壁を越えて、本当に欲しい人材に出会うための第一歩として、ぜひお役立てください。
目次
はじめに:なぜ今、外国人採用が注目されるのか
人手不足が進む日本

現在、多くの企業が「人が採れない」「採っても定着しない」という深刻な採用課題に直面しています。
特にサービス業・小売業・製造業などでは、求人を出しても応募が来ないという状況が珍しくなくなっています。
背景には、少子高齢化による労働人口の減少や都市部への人材集中、若年層の働き方の多様化など、複数の構造的要因があります。
その結果、「人材の質より、まず人がいない」という事態に陥り、人手不足が事業の成長や安定的な運営を妨げているのが現状です。
外国人採用が広がる
こうした状況を受けて、外国籍人材の採用が注目を集めています。
実際、厚生労働省の最新データ(令和6年10月末)によると、日本で働く外国人労働者は230万人を超え、前年比で約25万人(+12.4%)増加。
外国人を雇用する企業も34万社を超え、過去最多を更新しています。

出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」令和6年(2024年)
国籍別では、ベトナム(57万人)・中国(41万人)・フィリピン(25万人)が上位を占めており、さまざまなバックグラウンドを持つ人材が日本で活躍しています。
さらに注目すべきは、在留資格別で「専門的・技術的分野の在留資格」の人数が初めて最多となった点です。
これは、日本企業が即戦力の外国人材を本格的に活用し始めていることの現れでもあります。
加えて、政府も「特定技能」や「高度人材ポイント制度」などを通じて、外国人が日本で働きやすい環境づくりを推進中です。
今や、外国人採用は一部の業界・企業に限った特別なものではなく、多言語対応や国際感覚を求める企業にとって、現実的かつ有力な選択肢になりつつあります。
外国人採用のメリットとは?

若手・専門人材を確保できる
日本国内では若年層の減少が進んでおり、特に地方企業や中小企業では若手人材の採用が困難な状況です。
その一方で、外国人材は20〜30代の若い世代が多く、意欲的な方が多いのが特徴です。
また、海外の大学や専門学校で専門分野を学び、日本に就職を希望する人も増えています。
貿易事務やマーケティング、機械設計やITエンジニア、ホテル・観光分野の経験者など、一定のスキルを持った即戦力人材に出会える可能性も高まります。
採用ターゲットを日本人だけに限定せず、グローバルに視野を広げることで、より多くの優秀な人材と出会えることが最大のメリットです。
多言語対応でビジネス拡大
英語・中国語・韓国語・ベトナム語など、多言語に対応できる人材を採用することで、
企業の営業・接客・サポート体制に大きな強みが生まれます。
特にインバウンド(訪日外国人観光客)や越境EC(海外向け通販)など、国際市場と関わるビジネスでは、語学力が直接的な競争力になります。
例えば、外国人顧客対応が必要なホテルや観光業、不動産業、海外との取引がある製造業など、
外国語を活かせるシーンは年々広がっています。
外国籍社員がいることで、新しい市場開拓の足がかりになるだけでなく、社内の国際感覚の向上にもつながります。
組織に多様性と活気が生まれる
外国人材が加わることで、企業内に新しい価値観や文化的背景が持ち込まれます。
これにより、「うちの会社はこうだから…」という固定観念にとらわれず、柔軟な発想や新しい視点が自然と生まれやすくなります。
また、多様な背景を持つメンバーがいることで、社内コミュニケーションの質も変わります。
相手の立場や考え方を尊重する姿勢が根付き、チームの一体感が高まったという企業も多くあります。
さらに、企業がダイバーシティを実践している姿は社会的な評価の向上にもつながります。
外国人材を採用することは、単なる人手不足解消にとどまらず、企業の文化や価値を豊かにする一手にもなり得るのです。
外国人採用の課題と注意点
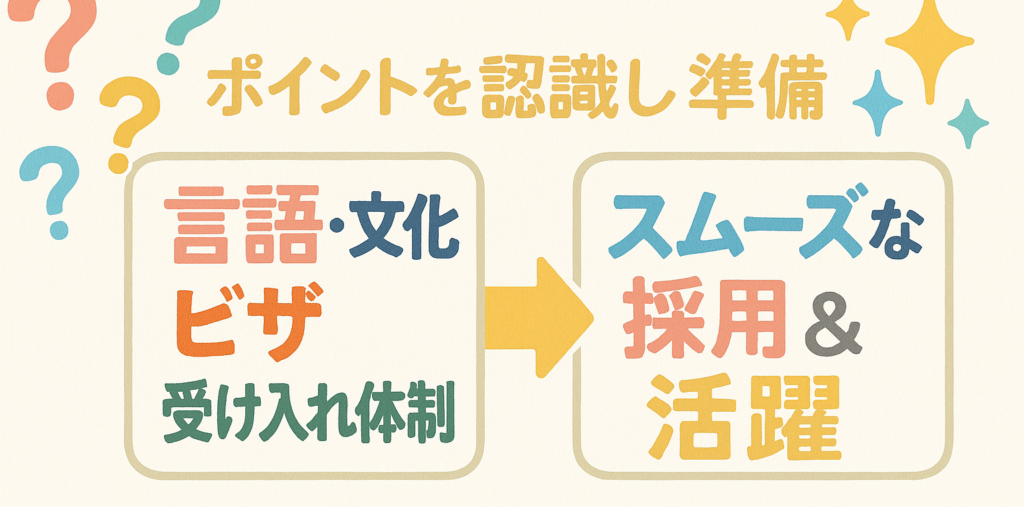
言葉・文化の壁によるトラブル
外国人採用でよく挙げられるのが、「言語や文化の違いによる」ちょっとしたすれ違いです。たとえば:
- 指示の細かいニュアンスが伝わらなかった
- 曖昧な表現がそのまま受け取られてしまった
- 「報・連・相」や暗黙のルールに慣れておらず、報告のタイミングがずれた
こうしたことは、日本の職場文化にまだ不慣れな段階では、珍しくありません。
特に“察する文化”が強い日本においては、言葉を補う明確な説明が必要になる場面もあります。
とはいえ、日本での就労経験を持ち、N2以上の日本語力を備えた外国籍人材であれば、こうしたギャップは最小限。
最初のすり合わせさえできれば、すぐに馴染み、力を発揮できる方がほとんどです。
また、企業側もこういった違いを“最初から想定しておく”だけで、未然に防げるトラブルがぐっと減ります。
ビザ手続きなど事務負担
外国人を雇用する場合、「就労ビザ(在留資格)」の取得や変更が必要です。
また、入社後にも外国人雇用状況の届け出(ハローワーク)が義務付けられています。
採用が決まった後も、
- 在留資格の種類の確認
- 必要書類の作成
- 入国管理局への申請
- 入社時の生活サポートや引越しの支援
など、通常の採用に比べてやや煩雑な手続きが発生するのが現実です。
ただし、最近では行政書士や支援機関に一部業務を委託することも可能です。
必要に応じて外部の専門家を活用しながら、企業の負担を最小限に抑える方法を検討すると良いでしょう。
職場の受け入れ準備
採用するだけで終わりではなく、入社後の定着と活躍ができる環境づくりも欠かせません。
たとえば、
- 社内に「何でも相談できる」メンターや相談窓口を設ける
- 社内研修に異文化理解を取り入れる
- 多言語マニュアルやツールを用意する
といった対応が重要です。
また、最初の数ヶ月は「仕事+生活」の両面で不安を抱える人も多いため、引越しや生活環境のサポートがあると安心して働き始められます。
外国人材が長く活躍できるかどうかは、「企業側の準備」が大きなカギを握っています。
採用前から、“受け入れるための準備”をしっかり整えておくことが、トラブルを防ぎ、企業にとっても良い結果につながります。
こう聞くと「大がかりな準備が必要なのでは?」と思うかもしれませんが、多くの場合は“ちょっとした工夫”と“気配り”で十分対応可能です。
すでに一定のビジネスマナーを身につけている方も多いため、特別な対応を必要としないケースも多いです。
ポイントは、「企業側の準備は“万全”でなくていい」。
“まずは一緒に働く姿勢”があれば、必ず乗り越えていけるということです。
採用前に知っておくべき制度とルール

外国人採用においては、日本人の雇用とは異なる法律やルールがいくつか存在します。
特に重要なのが「在留資格」と「労働条件」に関する知識です。
何か難しそうに聞こえるかもしれませんが、要は「許可されていない仕事で働いてはいけません」「不当な扱いをしてはいけません」ということなので、特別に難しい話ではありません。
以下、ポイントを説明していきます。
在留資格の種類と就労条件
外国人が日本で働くには、在留資格(就労ビザ)が必要です。
在留資格には複数の種類があり、それぞれ就労できる職種や内容が定められています。
たとえば:
| 在留資格 | 主な職種例 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 事務、通訳、マーケティング、ITなど |
| 特定技能(1号・2号) | 飲食、宿泊、介護、建設など |
| 留学・家族滞在 | 原則として就労不可(資格外活動許可で制限付き就労は可) |
企業が雇用する際は、その人のビザでどの仕事が許されているのかを正確に確認しなければなりません。
もし、認められていない業務に従事させると、違法就労助長罪に問われるリスクもあるため、十分な注意が必要です。
労働法や待遇に関する注意点
外国人だからといって、労働条件を不当に下げることは法律で禁止されています。
労働基準法や最低賃金法など、日本の労働関連法令は外国籍社員にも同様に適用されます。
つまり、
- 労働契約書の締結
- 給与・労働時間・休暇などの条件提示
- 雇用保険・社会保険の適用
といった基本的な取り扱いは、日本人社員と同様に行わなければなりません。
雇用時・退職時の法的手続き
企業が外国人を採用・退職させた場合は、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
- 提出先:所轄のハローワーク
- 提出時期:採用日または離職日から14日以内
- 内容:氏名、在留資格、在留期間、職種など
この届出を怠った場合、30万円以下の罰金対象になることもあるため注意が必要です。
違法就労させた場合のリスク
意図せずに在留資格に合わない業務を任せてしまった場合でも、「知らなかった」では済まされません。
違法就労助長罪に問われた企業は:
- 刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
- 社会的信用の失墜
- 入管庁からの指導・是正勧告
といった重いリスクを負う可能性があります。
採用前のビザ確認と、採用後の適正な管理体制は、必ず整えておきましょう。
外国人採用の進め方:ステップ解説

ステップ①:採用計画を立てる
まずは、自社が求める人材像や業務内容を明確に定義することが重要です。
- 日本語レベルはどの程度必要か?
- 英語や他言語も必要か?
- 技術や資格の有無は必須か?
- 社内のサポート体制はあるか?
これらを整理することで、募集段階でのミスマッチを防ぐことができます。
ステップ②:募集・選考を進める
募集方法としては、以下のような手段があります。
- 外国人向け求人サイト
- 外国人材に強い人材紹介会社
- 自治体や登録支援機関などの窓口
選考時には、以下の確認が重要です:
- 日本語能力試験(JLPT)などを参考にした語学力
- 在留資格の種類と内容
- 長く働く意欲・定着可能性
面接ではスキルだけでなく、文化や価値観のすり合わせも意識しましょう。
ステップ③:採用決定後のビザ手続き
内定が決まったら、就労可能な在留資格があるかを確認し、必要に応じて在留資格の変更や申請を行います。
主な手続きの流れ:
- 雇用契約書の作成
- 必要書類の準備(会社概要・職務内容など)
- 入管への申請(在留資格変更 or 就労資格証明書)
- 入管審査(通常1〜2ヶ月)
- 在留カードの交付
ただし、既に有効な在留資格を持っており、前職と同じ内容での業務に就く場合は、入社前に在留資格変更の手続きを行う必要はありません。
その場合は、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」を行うだけで、すぐに入社できるケースも多くあります。
このように、ケースによって必要な手続きが異なるため、心配な場合は専門家へ確認すると安心です。
ステップ④:入社前後の受け入れ体制づくり
採用が決まったら、入社までの準備も重要です。
- 住宅の手配や生活支援(地方採用や海外在住者の場合)
- 初日の業務マニュアルや説明資料の準備
- 同僚への紹介・受け入れ体制の周知
- 外国語に対応した社内マニュアルや掲示物の整備
外国人社員が初日から安心して働けるよう、「何につまずくか」を想定して、先回りして準備しましょう。
採用後に定着・活躍してもらうために
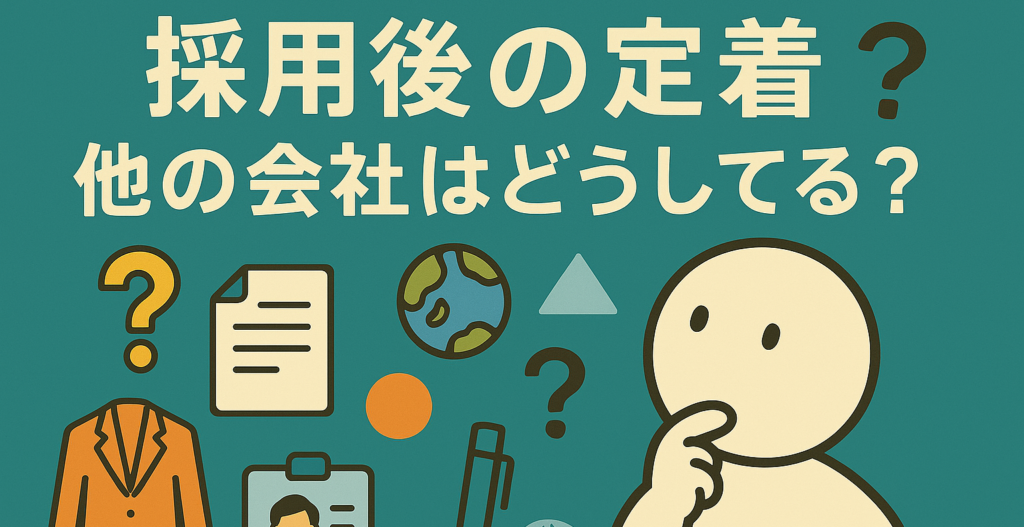
外国人採用も日本人採用と同じく、「採用して終わり」ではありません。
せっかくご縁があって入社してもらった人に、長く安心して働いてもらうには、それなりの準備や配慮が必要です。
ここでは、実際に外国籍人材を採用している企業様が行っている「採用後のフォロー体制」の例をご紹介します。
すべてを導入する必要はありませんが、自社の体制に合うものがあれば、参考にしてみてください。
社内受け入れ体制の整備
外国人社員が安心して働けるよう、最初の受け入れ体制がとても大切です。
▷ 相談窓口の設置
仕事だけでなく、住まいや生活に関する悩みもサポートできるよう、社内に相談窓口を設けている企業もあります。
▷ 異文化理解の研修
外国籍社員と関わるメンバー向けに、文化や習慣の違いを学ぶ研修を実施し、コミュニケーションの土台をつくるケースもあります。
コミュニケーション支援の工夫
語学や文化の違いをフォローすることで、職場での不安やミスを防ぐ効果も。
▷ 多言語の業務マニュアル
英語や中国語などでマニュアルを用意している企業では、業務の理解がスムーズになる傾向があります。
▷ 日本語学習のサポート
外部の日本語教室の紹介や、簡単な日本語教材の配布を行う企業もあります。
業務指導とキャリア支援
「この会社で長く働けそう」「ここなら成長できそう」と思ってもらうことが、定着の鍵です。
▷ キャリアパスの提示
将来的な役割や昇格の流れを伝えることで、目標を持ちやすくなります。
▷ メンター制度
1人ではなく、誰か相談できる人が社内にいるというだけで、安心感が変わってきます。
定着とモチベーションの向上
「この職場が自分の居場所」と感じられる工夫も、実は定着に大きく影響します。
▷ 評価制度の工夫
多様な背景を持つ社員に配慮した評価制度を取り入れている企業も増えています。
▷ 社内イベントの実施
歓迎会や文化紹介イベントなど、ちょっとした場を通して、社内のつながりが深まります。
外国人採用だからといって特別な対応が必須というわけではありません。
ただ、日本人の採用と同じく、「安心して働ける環境づくり」はとても大切です。
紹介した事例の中から、自社に合うものだけでも取り入れてみると、長期的な活躍につながるかもしれません。
活用できる支援制度・外部サービス
外国人採用を進める上で、国や自治体、専門機関などが提供する支援制度やサービスを活用することで、負担を軽減し、よりスムーズに進めることができます。ここでは、特に知っておきたい代表的な支援をご紹介します。
国や自治体の助成金・支援策
外国人雇用に関連する公的支援として、国や地方自治体が提供している助成金制度があります。
- 例:就労環境整備助成金(厚生労働省)
→ 外国人労働者の受け入れに伴う、就労環境の整備(マニュアル作成、研修実施など)に対する費用の一部を補助。 - 地方自治体の独自助成制度
→ 東京都や大阪府などでは、外国人雇用促進に向けた独自の支援策を設けている場合も。最新情報をチェックしましょう。
📌【ポイント】
申請には「雇用契約書」や「計画書」など事前準備が必要です。早めの確認が重要です。
詳しくはこちら
公的機関の相談窓口・情報源
外国人の雇用に関する相談は、ハローワークや各自治体の外国人相談窓口でも対応しています。
外国人総合相談センター(全国各地)
→ 多言語対応で、雇用主と外国人本人の両方に対応してくれるケースもあります。
ハローワークの外国人雇用サービスコーナー
→ 在留資格の種類に応じた就労可否の確認や、求人票の書き方の相談が可能。
民間サービスの活用と選び方
行政手続きに不安がある企業は、登録支援機関や外国人材紹介に特化した人材会社を活用するのも一つの手です。
- 登録支援機関
→ 特定技能人材を受け入れる企業の代わりに、生活サポートや書類管理を実施する機関。法務省に登録されており、信頼性の高い支援が受けられます。 - 外国人材紹介会社
→ 求人要件に合った候補者の紹介、ビザ取得サポート、入社後の定着支援までを一括対応してくれるサービスが増えています。
📌【ワンポイント】
委託先を選ぶ際は「外国人のサポート実績」「就労ビザの取り扱い経験」「業界への理解」の3点を確認すると安心です。
まとめ:外国人採用を成功させるために

本記事では、外国人採用を進めるうえで押さえておきたい基本的な知識と実務のポイントを解説しました。
特に重要となるポイントは、以下の5点です。
✅ 外国人採用の5つの基本ポイント
- 在留資格の確認が最優先
就労可能な在留資格かどうかを確認し、認められていない業務に就かせないことが重要です。 - 労働条件や法的手続きは日本人と同様に
労働基準法・社会保険・雇用契約の取り扱いは、日本人社員と同じルールが適用されます。 - 入社後の受け入れ体制が定着を左右する
相談窓口や多言語対応マニュアル、キャリア支援など、安心して働ける環境づくりがカギとなります。 - 国や自治体の支援制度を有効に活用する
助成金や相談窓口など、制度をうまく利用することで、採用・定着までの負担を軽減できます。 - すべてを完璧にする必要はない
必要な部分から少しずつ整備を進めることで、自社らしい外国人採用の形をつくっていくことが大切です。
外国人材の採用は、特別な取り組みのように見えるかもしれませんが、
基本的なルールと配慮を押さえれば、日本人採用と大きく変わるものではありません。
本記事が、貴社にとって外国人採用を前向きに進めるためのヒントになれば幸いです。
ビザ手続きから定着支援まで、無料でご相談受け付けております。
無料相談フォームへ